公開日 2020年10月21日
更新日 2021年03月10日
・上乗せ基準
国が設定する一律の排出基準や排水基準では、その地域の自然的・社会的条件から判断して人の健康保護や生活環境保全が十分でないとき、都道府県が関係する法律に基づき条例で定めることができる基準で、国が設定する基準より厳しい基準。
・環境アセスメント(環境影響評価)
公害の発生や自然環境の破壊はいったん起こるとその対策には多くの費用と年月とを必要とし、また、完
全な回復も難しくなる。このため、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施に際し、その環境影響について事前に調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る事業者が自ら環境の保全について適正に配慮しようとするもの。
・環境基準
「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」(環境基本法第16条)のことで、現在は、大気汚染、水質汚濁、騒音及び土壌汚染について定められている。
・環境ホルモン
正式には「外因性内分泌かく乱物質」と呼ばれている。体内に取り込むとホルモンに似た動きをする科学物質で、疑われている物質として除草剤・殺虫剤に用いられるDDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)、界面活性剤のノニルフェノール、プラスチックの原料のビスフェノールA、船底の塗料成分の有機スズなどが知られている。我が国では有機スズによるイボニシの生殖器の異常などが報告され、ラットや魚類などを使った動物実験では、オスがメス化するなど、生殖器や性行為に影響を与えることが確認されている。
・環境ラベル
 |
エコマーク
エコマークは、身の回りの商品の中で、特に環境保全に役立つ商品のシンボルマークである。英語の「地球」「環境」を意味する頭文字「e」が人間の手の形になってやさしく包み込んでいるイメージで作られた。 |
|---|---|
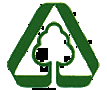 |
グリーンマーク
グリーンマークは古紙を原料に利用した製品であることを容易に識別できる目印である。原則として40%以上利用した製品につけられている。 |
・規制基準
工場・事業場が守らなければならない騒音、振動、悪臭等の基準。この基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれていると認められるときは、改善のための措置が取られる。
・原因者負担の原則(PPP)
経済開発協力機構が1972年に採択した「公害防止費用は公害発生の原因者(polluter)が負担(pay)する」という決議が基となり、公害対策の基本理念となっている原則(principle)で、PPPの略称が広く使用されている。
・公害、典型七公害
環境基本法で定義する「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることと定義されている。この七公害を典型七公害と呼んでいる。
・公害防止協定
行政庁や住民団体等と企業等の間で、公害防止のために必要な措置を取り決める「協定」のことをいう。
・国際標準化機構(ISO)
1947年に設立された世界共通の規格等の設定を行う民間組織。品質管理・品質保証システム規格のISO9000シリーズと環境管理・環境監査規格のISO14000シリーズは世界の多くの事業所が認証取得を受けている。特に、ISO14001は環境マネジメントシステムと呼ばれ、取得企業数が急増しており、あらゆる業種における自主的、積極的な環境への取組が浸透しつつある。
・こどもエコクラブ
小・中学生を対象とした環境活動のクラブで、平成7年度に環境省の事業として発足し、平成24年度からは日本環境協会(現公益財団法人)が継承。子どもたちの地域における自主的な環境学習や実践活動を支援するもので、全国で約8万2千人(令和2年度)が参加している。
・ダイオキシン類
ポリ塩化ジベンゾパラジオキシンとポリ塩化ジベンゾフランにコプラナーPCBを加えた総称で、222種類の異性体があるといわれており、その中には非常に毒性の強いものもある。ベトナム戦争で米軍が使用した枯れ葉剤にも含まれ、多くの奇形児を生んだ原因とされている。ダイオキシンは、ごみ焼却施設からの排出が8~9割を占めており、主に食物を通じて人体に蓄積される。
・排出基準
大気汚染防止法では工場などのばい煙発生施設について排出基準が定められている。硫黄酸化物については着地濃度によってK値規制という特殊な形で規制される(大気の項参照)。ばいじんや有害物質については施設の種類や規模ごとに排出口における濃度について許容限度が定められている。また、ばいじん及び有害物質については都道府県が条例により厳しい上乗せ基準を定めることができる。
・排水基準
水質汚濁防止法では、工場などからの排水の公共用水域への排出について健康保護(有害物質)項目及び生活環境項目について排出水中の濃度を規制している。これを排水基準という。また、都道府県は条例によって排水基準より厳しい上乗せ基準を定めることができる。
(2) 大気・悪臭関係
・硫黄酸化物(SOx)
二酸化硫黄(SO2)、無水硫酸(SO3)などの総称で、石油・石炭の燃焼等によって生じる。大気汚染の主体は二酸化硫黄だが、無水硫酸も空気中の水蒸気と結合して硫酸ミストを生成し、動植物や人体に影響を与える。
二酸化硫黄は、人が吸うと喉や肺を刺激して気管支炎や上気道炎などを起こし、細菌やウイルスに対する抵抗力を低下させるとされている。
・一酸化炭素(CO)
炭素含有物が不完全燃焼したときに発生する無色無臭の気体であり、血液中のヘモグロビンの酸素運搬作用を阻害し、中枢・末梢神経のマヒ状態を起こす。発生源は自動車の排気ガスが大部分を占めている。
・オキシダント
大気中窒素酸化物・炭化水素などが紫外線の作用で、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生じた酸化性の強い物質。光化学スモッグの原因となる。
・K値規制
大気汚染防止法では各地域別に許容できる最大着地濃度を設定し、各ばい煙発生施設ごとに次式により硫黄酸化物の排出許容量を計算できる。
q=K×10-3 ×He2
q:1時間単位の汚染排出許容量
He:有効煙突高さ
残る係数はK値といわれ、地域ごとに定められており、小樽市は8となっている。このK値が小さいほど規制が厳しい。
・酸性雨
化石燃料の燃焼等に伴い排出される硫黄酸化物等により雨水が酸性化すること。pH5.6以下の雨水を広い意味で酸性雨と定義している。これによる被害は今では欧州全体の湖沼、森林、建造物に及んでいる。また、日本でも建造物などに酸性雨が原因かと思われる被害が発生している。
・三点比較式臭袋法(官能試験法)
昭和52年、官能試験法調査報告書(環境庁)で行政的評価法として最も優れたものの一つとされており、平成7年度には悪臭防止法における臭気濃度の測定方法の一つに採用された。測定方法は、3つの袋(ポリプロピレン製)の1つに所定の臭気を入れ、他の2つには、無臭空気を入れ、人の嗅覚で付臭袋を選択させ、順次段階的に希釈した付臭袋を正しく選択できなくなるまで行い、計算で臭気濃度を求めるものである。
・炭化水素(HC)
炭素と水素の化合物の総称。石油系燃料及び有機溶剤の主成分であるが、自然環境大気中にも微量ながら広く存在し、その3分の2以上がメタンである。メタンを除いた炭化水素を非メタン系炭化水素といい、大気中で窒素酸化物と反応して光化学オキシダントを生成し、大気汚染源となる。自動車の排気ガスや、その他石油製品を扱う施設からの漏えいなどが主要な人工発生源である。
・窒素酸化物(NOx)
一酸化窒素及び二酸化窒素を主体とする窒素酸化物は、重油、ガソリン、石炭などが高温で燃焼するときに発生し、発生源は自動車エンジン、発電所ボイラー、工場、家庭暖房など広範囲にわたる。工場や自動車などの発生源から大気中に排出される段階では、ほとんどは一酸化窒素が占めるが、大気中を移動する過程で大気中の酸素と反応して二酸化窒素に酸化されるため、大気中では一酸化窒素と二酸化窒素が共存している。
一酸化窒素は、二酸化窒素に比べその毒性は低いとされている。また、二酸化窒素は、粘膜刺激性を持ち、呼吸気道及び肺に対して毒性を示す。
・TEQ
毒性等量。ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの量に換算して表したもの。
・日平均値の年間98%値
環境基準達成状況の判定に使用される値で、1年間に得られた1日平均値を濃度順に並べて、低い方から98%目に相当する日の1日平均値をいう。なお、98%にあたる測定日は、小数点以下四捨五入して算出する。
・日平均値の年間2%除外値
環境基準達成状況の判定に使用される値で、1年間に得られた1日平均値を濃度順に並べて、高い方から2%の範囲にあるものを除外して残った1日平均値の最高値をいう。2%を除外する日数は、小数点以下四捨五入して算出する。
・m3N(ノルマル立方メートル)
気体の容積を表す単位であり、m3Nは温度0℃、1気圧における気体の容積を示す。
・微小粒子状物質(PM2.5)
大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μm以下のものをいう。粒径が非常に小さいため肺の奥深くまで入りやすいことから、ぜん息や気管支炎を起こす確率が高くなるなど、健康に及ぼす影響が大きい。
・ppm(ピーピーエム)、ppb(ピーピービー)
ごく微量の物質の濃度等を表す単位。
ppm=100万分の1 1ppb=10億分の1
・浮遊粒子状物質(SPM)
大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が10μm以下のものをいう。大気中に比較的長時間滞留し、気道又は肺胞に沈着し呼吸器系統に影響を及ぼす。
・μg(マイクログラム)、ng(ナノグラム)、pg(ピコグラム)
ごく微量の物質の重さを表す単位。
1μgは1gの百万分の1、1ngは1gの10億分の1、1pgは1gの1兆分の1の重さを表す。
・有害大気汚染物質
大気汚染防止法では、「継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれがある物質で大気汚染の原因となるもの」と定義され、有害大気汚染物質である可能性のある物質は数百種類とされ、現在調査が進められている。その中から、人の健康に係る被害が生ずるおそれに関して、ある程度高いと考えられる22物質が現在「優先取組物質」として選定されている。そのうちベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンについては早急に抑制しなければならないとする「指定物質」に指定されており、排出施設からの排出抑制基準や環境基準が定められている。
| 優先取組物質(23物質) | |
|---|---|
|
|
(3) 騒音・振動関係
・暗騒音
ある音を対象として考える場合、その音がない時のその場所における音を対象の音に対して暗騒音という。例えば、ある地点における送風機の騒音を測定したいときは、その送風機が稼動していない時に測定した音(自動車騒音や虫の声など)が暗騒音となる。
・環境騒音
ある地域で、通常そこに存在する不特定多数の音源から発生する総合された騒音をいう。
・90%レンジ
工場騒音及び建設作業騒音の不規則かつ大幅に変動する騒音の評価方法として用いられている。累積度数曲線の下端及び上端でそれぞれ5%の度数を除いた変動幅をいい、累積度数5%・95%に対する値を90%レンジの下端値・上端値という。
・振動、振動レベル
公害として問題にされる振動とは、工場、建設作業、交通機関などから発生する振動が建物に物的被害を与えたり、住民の生活に不快感等の影響を与えるものをいう。また、振動レベルとは、振動加速度の実効値に対し、振動感覚補正特性(鉛直・水平)や動特性(630msec)によって、人体の感覚に基づく補正をして得られる値で、単位として「dB」が用いられる。
・騒音、音圧レベル(騒音レベル)
「好ましくない音」の総称であり、睡眠を妨げたり、会話を妨害するなど生活環境を損なうような不愉快な音、邪魔な音など「ないほうが良いとされる音」である。また、ある音を日本工業規格に定める普通騒音計などで測定して得られる指示値を音圧レベル(騒音レベル)と呼び、単位は「dB(A)」である。音圧レベルは耳の感覚を計器の回路として組み込むことにより聴感補正されたもので、音の大きさのレベルを近似的に表す。
・中央値(L50)
騒音計の指示値で、そのレベルより高いレベルと低いレベルの時間とが半分ずつあるようにとった値。
・低周波音(低周波空気振動)
低周波音は、一般の人間の耳で聞き取ることができる範囲以下の低い周波数の空気振動で、単位はデシベル(dB)が用いられる。窓ガラス等を振動させて二次的騒音を発生させたりするほか、そのレベルによっては生理的影響が考えられる。
・等価騒音レベル(Leq)
時間とともに変化する騒音のエネルギーを平均した騒音レベル。国外で多く用いられるようになってきており、日本でも平成11年4月1日より「騒音に係る環境基準」は等価騒音レベルが用いられている。
・特定建設作業
指定地域内において、著しい騒音・振動を発生させる建設作業であって、政令で定められたものをいい、杭打ち機を使用する作業、さく岩機を使用する作業及びブレーカーを使用する作業などがある。
・80%レンジ
振動加速度レベルの不規則かつ大幅に変動する場合の評価方法として用いられている。累積度数曲線の下端及び上端でそれぞれ10%の度数を除いた変動幅をいい、累積度数10%・90%に対する値を80%レンジの下端値・上端値という。
・面的評価
幹線道路に面した地域で、道路端から50mの範囲にあるすべての住居等の騒音レベルについて、実測や推計によって環境基準に適合している戸数及び割合を算出し評価する方法をいう。
・要請限度
自動車交通騒音・振動が、総理府令で定める限度を超えて発生し、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるとき、騒音規制法及び振動規制法の規定により、市町村長は公安委員会に対し道路交通法の規定による車両の通行の制限について要請することができる。また、道路管理者又は関係行政機関に、道路構造の改善について意見を述べることができると定められている。
(4) 水質・地下水関係
・アンモニア性窒素
アンモニウムイオンをその窒素量で表したもの。タンパク質、尿素、尿酸などの有機性窒素の分解により生成するもので、水の汚染度を示す指標の一つとなる。主な発生源は、し尿、生活排水、肥料、化学工場の排水など。
・SS(浮遊物質)
水に溶けない粒径2mm ~1μmの懸濁の総称。SSが多くなると、水は濁り、光の透過を妨げ、水域の自浄作用を阻害したり、魚類の呼吸に悪影響を及ぼす。
・n-ヘキサン抽出物質
ノルマルヘキサンという溶剤に溶ける油分等をいい、排水中の鉱油、動植物油を表す指標。鉱油は、魚類に付着すると異臭魚の発生原因となる。
・クロム (三価クロム、六価クロム)
耐食性に優れ、鉄と合金をつくりステンレススチールとなる。通常、クロムには三価クロム化合物と六価クロム化合物があり、六価クロムは三価クロムに比べて毒性が強い。また、六価クロムは還元されて三価クロムに、三価クロムは酸化されて六価クロムに変化することがある。六価クロムを大量に摂取すると嘔吐、腹痛、けいれんを起こし死に至る場合がある。
・公共用水域
河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれらに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共に供される水路をいう。なお、現に終末処理場がある下水道は、公共用水域に含まれない。
・シアン
青酸カリ等で知られる有害な物質である。シアンが作用すると、通常は数秒ないし数分で中毒症状が現れ、頭痛、めまい、意識障害、けいれん、体温降下を起こし、数分で死に至る。少量摂取の場合は頭痛、耳鳴り、嘔吐が起こる。
・COD(化学的酸素要求量)
酸化剤を用いて水中の有機物を酸化分解する際に消費される酸素量をmg/ℓで表したもの。数値が高いほど水中の汚濁物質の量が多いことを示す。海域や湖沼の汚濁を表す良い指標となる。
・水 銀
常温で唯一の液体の金属。湿った空気中で酸化物になりやすく、有毒な物質である。神経系をおかし、手足のふるえを起こしたり言語障害、食欲不振、視力聴力の減退をもたらす。
・生活排水
家庭生活からの排水。し尿と台所排水、風呂排水、洗濯排水などその他の諸排水からなり、後者を特に生活雑排水という。下水道普及地区以外では、し尿はし尿処理場又は浄化槽で処理されるが、雑排水は無処理で側溝を経て公共用水域に放流されることが多く、水域の汚染の大きな原因となっている。
・大腸菌群数
腸内細菌に属するグループで幾種類かのものの総称であり、病原性のものと非病原性のものがある。大腸菌群が検出されるということは、人畜のふん尿が混入している疑いを示す。
・DO(溶存酸素量)
水中に溶けている酸素の量をmg/ℓで表したもの。水中に汚染源となる有機物が増えると、それを分解する微生物により酸素が消費されDOが減少し、魚などがすめなくなる。
・75%水質値
BOD、CODの環境基準の長期的評価に用いる値。n個の年間の日平均値を小さいものから順に並べた0.75×n番目の値(整数でない場合は切り上げ)。単に75%値ともいう。
・BOD(生物化学的酸素要求量)
微生物によって水中の有機物が酸化分解される際に消費される酸素の量をmg/ℓで表したもので、その数値が大きければ、その水中には汚染物質(有機物)が多く、水質の汚濁が進んでいることを示す。通常、5日間に消費される酸素量で示し、河川の汚濁を表す良い指標となる。
・PCB(ポリ塩化ビフェニル)
不燃性で、化学的にも安定しており、熱安定性にも優れた物質で、その使用範囲は絶縁油潤滑油、ノンカーボン紙など多方面にわたっている。カネミ油症事件の原因物質で新しい環境汚染物質として注目され、大きな社会問題となったため、現在は製造禁止となっている。
・pH(水素イオン濃度指数)
酸性、アルカリ性を示す指標で、7.0が中性、これより数値が小さくなるほど強い酸性を示し、数値が大きくなるほど強いアルカリ性を示す。
・リ ン
リンは家庭雑排水や工場排水などに多く含まれ、これらが川や湖に大量に流れ込むと、プランクトンや水中生物が異常増殖し、溶存酸素の不足などの水質悪化につながる。
(5) その他
・アジェンダ21
1992年、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開かれた「地球サミット(環境と開発に関する国連会議)」で、持続可能な発展のための21世紀に向けた具体的な行動計画「アジェンダ21」が採択された。前文及び1社会的・経済的側面、2開発資源の保護と管理、3主たるグループの役割の強化、4実施手段の4部から構成されている。大気保全、森林減少、砂漠化、生物多様性、淡水資源、海洋保護、廃棄物等の具体的な問題についてのプログラムを示すとともに、その実施のための資金メカニズム、技術移転、国際機構、国際法の在り方等についても規定している。
・オゾン層の破壊
特定フロン等の大気中への放出に伴い、成層圏のオゾン層が破壊され、その結果、有害紫外線が増大し、皮膚がんが増える等の健康影響や生態系への悪影響をもたらすこと等に加え、気候に重大な影響を及ぼすことが懸念されている。
・海洋汚染
今日、世界の海洋全般に及ぶ油、浮遊性廃棄物、有害化学物質等による汚染の進行により海に生育・生息している多くの生物に悪影響を与え、生態系をも変えようとしている。
・森林(特に熱帯雨林)の減少
焼畑移動耕作、農地への転用、過放牧、商業材の伐採等により、毎年熱帯林が1,130万ha(本州の約半分の面積)減少していると推測されている。熱帯林の減少に伴い、開発途上国の産業・生活基盤や野生生物の生息地が損なわれるほか、気候変化や土壌流出等の影響も生じている。
・地球サミット(環境と開発に関する国連会議)
1992年6月3日から14日まで、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開かれた国連人間環境会議。100か国以上の政府首脳が一堂に会し、地球環境の保全に関する国際協力について討議された。リオ宣言、アジェンダ21等が採択された。
・地球の温暖化
大気中の二酸化炭素、フロン、メタン等の温室効果をもつガスの濃度上昇により地球が温暖化するおそれがあり、このまま推移すれば、2100年には平均気温は最大で4.8℃、海面は最大で82cm上昇すると予測されており、異常気象の発生、農業生産、生態系、国土保全等への影響が懸念されている。
・野生生物の種(生物多様性)の減少
地球上の未知の種を含む総生物種数は、3,000万種に及ぶと推測されている。人間活動により種の絶滅は進行しており、IUCN(国際自然保護連合)の2020年レッドリストによると、絶滅のおそれのある種として動植物32,441種が掲載されている。我が国の状況も同様で、160種の哺乳類では21%、約700種の鳥類では14%、約7,000種の維管束植物では26%が絶滅のおそれのある種と報告されている。(環境省レッドリスト2020)
・有害廃棄物の越境移動
有害廃棄物は安い処理費用あるいは規制の緩い国へと移動しやすいことから、先進国から開発途上国への有害廃棄物の不適正な輸出及びそれに伴う環境問題が発生し、環境への悪影響を及ぼしている。
